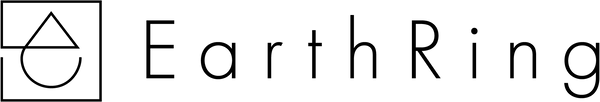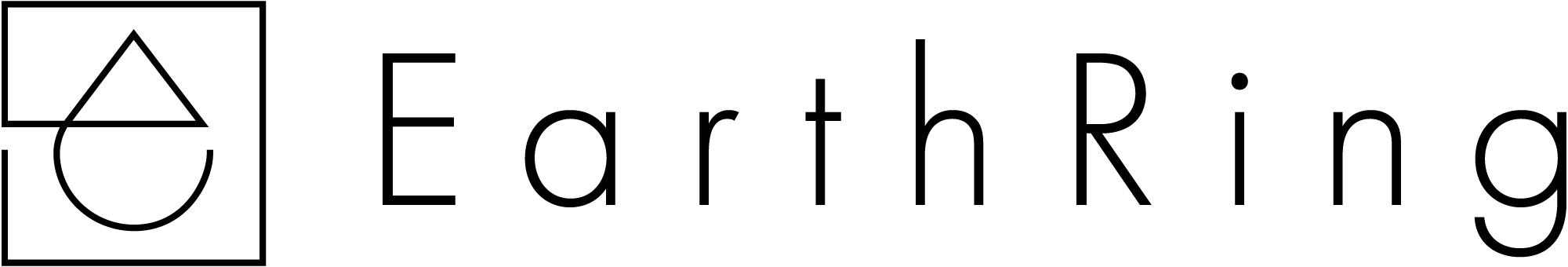第2回
サステナブル素材ストーリー
ホーリーバジル:耕作放棄地から生まれた“聖なる”香り

こんにちは、EarthRingです。
私たちが香りづくりに使う素材は、地元・白山市をはじめとした地域の生産者の方々によって手がけられたもの。「こんなものが余ってるんだけど」「何か香り商品にできないか?」……そうやって相談として持ち込まれた中で協業が始まり、試行錯誤を経て、今や私たちの定番商品になっているものがたくさんあります。
ここでは、そんな私たちEarthRingの香りづくりを支えている「素材」の背景、ストーリーについてお伝えしていきます。
第2回は、「ホーリーバジル」。お話を伺ったのは、白山市の旧鳥越地区でホーリーバジルの栽培を担う神子清水薬草組合の代表・山岸 惇さんです。

神子清水薬草組合・山岸惇さん
生まれ育った石川県白山市神子清水町(旧鳥越地区)にて、神子清水薬草組合の代表として耕作放棄地を活用した薬草栽培のプロジェクトを率いる。落ち着いた語り口調ながら、齢70歳を超えてるとは思えないハツラツとしたエネルギーを感じさせる。
ホーリーバジルってどんな植物?
EarthRingにとって、商品ラインナップの中でも特に自信作だといえるのが、ホーリーバジル。
なかなか精油として販売されているところが少なく、数ある植物からの香りの中でも希少性の高い香りといえます。

「バジル」と聞いてイメージされやすいのは、やはりイタリア料理を中心にピザやパスタによく使われている「バジル」の方ではないでしょうか?
イタリア料理で多用されるバジルはスイートバジル。スイートバジルはホーリーバジルと比べてもっと葉っぱが丸っこく、色味も薄い黄緑色。一方でホーリーバジルは、ガパオライスなどタイ料理などのアジア料理に使われます。見た目だけでなく、風味や香りも異なります。

ホーリーバジル1キロから取れる精油の量は、だいたい30〜40mlほど
EarthRingのホーリーバジル精油は、爽やかな中にも甘やかさもある仕上がりが特徴。スパイシーさとエレガントさのバランスが絶妙で、エキゾチックなアジアのリゾートを思わせる気品が漂います。
ホーリーバジルの精油を体感したことのあるアロマ業界の方でも、思わず「ホーリーバジルってこんないい香りだったと思わなかった!」というお褒めのお声をいただくほど。調香師を務める川上も、知っている人こそ体験してほしい、と胸を張るイチオシの品です。
その香り高さの秘密は、摘みたてをその日のうちに蒸留すること。新鮮なまま香りを抽出するので、生産者である山岸さんからも「(摘む前の状態と)変わらないね」とのお墨付き。

生産者の山岸さん。EarthRingのホーリーバジルの精油の香りを試して一言、
「さっき収穫してきたアレと変わらんな」
また、ホーリーバジルの収穫方法も重要です。収穫は手摘みで、必ず早朝に行います。これは、同じくホーリーバジルが大好きなミツバチ対策。昼間、花の蜜を吸いに来たミツバチが受粉を行うと、その時に花を押し広げることでその中から大事な精油成分が飛んでいってしまいます。そのため「早摘み」といって、ミツバチが行動しない時間帯に先んじて収穫してしまうわけです。早朝7時ごろから神子清水薬草組合の方々が手分けして収穫してくれたホーリーバジルを、9時ごろにEarthRingが取りに行き、蒸留所に戻ったらすぐに蒸留にかかります。

ホーリーバジルの花から蜜を吸うミツバチ
ひとたび摘んだら、そこからは時間の勝負。蒸留は摘んでその日のうちに行う。一度に70キロほど運び、蒸留器を3回転ほど回します。蒸留所はポタポタと落ちる音と華やかで爽やかな香りでいっぱいになります。


蒸留前、ハサミで雑味を生む部分を丁寧にカット。
シャキンシャキン、という小気味よい音が山に反響する。
ホーリーバジルの香りの効能
ホーリーバジルはインドの伝統医学アーユルベーダでも使用された歴史を持つ植物です。「母なる薬草」「不老不死の霊薬」として古代より生活に役立てられてきました。
主成分の「オイゲノール」には抗菌作用や抗ウイルス作用があり、風邪予防などに効果を発揮します。心身のバランスを整えたり、集中力アップにも最適です。瞑想やヨガの前に香りを焚くことで、空間浄化作用も。また、リラックス効果、ストレス緩和のある成分「リナロール」も含まれているため、繊細で心や体調が乱れがちな人にもおすすめ。日常に取り入れてみてほしい香りです。

【ホーリーバジル精油の効能】
◇心への作用(メンタルバランス)
緊張を和らげ、穏やかに、前向きに。
リラックス / ストレス緩和 / 抗うつ / 自律神経調整
・自律神経を整え、ストレスによる緊張や不安をやわらげる
・思考をクリアにし、瞑想や集中をサポートする
・感情の波を穏やかにして前向きな気持ちに導く
◇体への作用(コンディション)
穏やかに、内側からバランスを整える。
鎮痛 / 免疫サポート / 抗菌・抗ウイルス / 呼吸器の不調改善 / 巡りを促す
・呼吸を整え、巡りを促し滞りを解消してくれます。
・ストレス性、緊張性の不調に働きかけ体の内側からサポートする働きがあります。
・忙しさで乱れがちなバランス、女性のリズムを優しく整えます。
◇肌への作用(スキンケア)
コンディションを整え、健やかで清潔に導く。
抗酸化 / 抗菌 / 抗炎症 / 皮膚再生サポート / 血行促進
・肌荒れ、乾燥から肌を健やかに保ちたい時に
・エイジングケアやターンオーバーをサポート
・肌の血行、代謝を促し、いきいきとした印象へ
【こんな方におすすめ】
忙しい日々の中でも、自分をリセットしたい瞬間に。
・気圧や季節の変化に敏感な方
・清潔感や誠実さを香りで印象づけたい方
・ストレスや不安を感じやすい方
・現代的な生活リズムの乱れを感じる方
・ナチュラルに整える香りを求める方
【おすすめの使い方】
・アロマストーンやディフューザーで香りを広げ空気を浄化。朝の爽やかな目覚めをサポート。
・夜はお風呂に2〜3滴。湯気と香りで疲れを癒す。
・ハンカチに数的垂らし深呼吸。気分を切り替え、心のノイズを手放す。
・瞑想やヨガ、音楽や読書の時間に。呼吸と共に香りを感じ自分を調える。
🌿より詳しいホーリーバジル精油の効能やおすすめの使い方、購入はこちらをご覧ください
>>ホーリーバジル精油の効能やおすすめの使い方、購入はこちら
「耕作放棄地でホーリーバジルを栽培する」に至るまで
ホーリーバジルは、どうやって育てられているのか。お話を聞きに向かったのは、神子清水(みこしみず)町。白山市に合併する前は鳥越村であった地域です(※1)。今も地元では「鳥越」と呼ばれています。
※1 白山市は平成17年2月1日、1市2町5村(松任市、美川町、鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村、白峰村)の合併により誕生
ホーリーバジルの生産を担ってくれている神子清水薬草組合は、13名ほどで活動する有志団体。元々、EarthRingとの取り組みが始まる前に、8年ほど前から耕作放棄地を活用した薬草栽培を金沢大学と白山市とともに取り組んできました。
ホーリーバジルを作れる場所を探していたEarthRingの蒸留技師・大本は、そんな取り組みの話を聞きつけて山岸さんたちの薬草園を訪れます。

EarthRingの蒸留技師・大本。より澄んだ香りに仕上げるために
蒸留前にホーリーバジルに手を入れているところ
山岸さん:
「なんか、どっかからその薬草を作っとるちゃ聞いてきて。たしか、ふらふらっときたと思うんだよ」
突然現れた大本。当時を振り返って、山岸さんは笑います。

ホーリーバジルの畑で、山岸さん
「自分で食べるものは自分で作る」ーー自給自足スタイルの破綻が耕作放棄地を生んだ
耕作放棄地を活かし、そこからいかに価値を生むか。自分が生まれ育った土地が抱える難題に挑み続けてきた山岸さんたち。「山と森と水、そして人を守り、その恵みが未来へつながる幸せな循環を実現する」をビジョンとして掲げるEarthRingとしても、持続可能な新たな取り組みに挑戦したいーー。こうして、ホーリーバジルの栽培が始まることになりました。
でも、そもそも「耕作放棄地」が生まれる背景には、どんな時代の変化があるのでしょうか? 高齢化による担い手不足、と言ってしまえばそれまでですが、私たちはもう少し突っ込んで知りたい。EarthRingとしてのホーリーバジル栽培の前に現状を理解するため、山岸さんに詳しく伺ってみました。

山岸さん:
「ここら辺の集落はみんな兼業農家やった。兼業やから、合間見て百姓しとるようなもんや」
旧鳥越地区は、元々兼業農家が多い地域だったそう。山岸さんも、定年まではサラリーマンとして金沢にお勤めに行っていました。
「兼業農家」といっても、それで稼ぎを生み出すというよりは、自分たちで食べるものは自分たちで作るという、「自家菜園」のようなものだったと話します。
でも、仕事も農業もどちらもやっていたってこと? それってとても大変そうですが・・・
山岸さん:
「今はもう人口がだいぶ減ってきとうから。昔は、じいちゃん、ばあちゃんがおるがいね。自分の親もおるし。そういう人らがみんな畑をやっとったわけや。(当時の)わしらは若いから外へ出稼ぎ行っとるわけよ」

ホーリーバジル畑の周辺。山に囲まれ、平坦な土地は少ない。
先人たちは限られた土地を耕し、田畑としていた。
元々山間部で広い土地が確保しづらく、大規模な田畑を運営する家は少なかった旧鳥越地区。山間部を切り拓いてきた土地を各家族が少しずつ持ち、自分たちが生活するのに必要な分だけの食べ物を自分たちでつくる。そんな「農作業して自給自足でやっとった時代」が、だんだんと車に乗るようになったり、衣服など身の回りの物品を既製品として購入するようになると状況が変わってきます。
完全なる自給自足では暮らしが難しくなり、「外貨を稼ぐ」必要が出てきたため、家にいる若い世代が外に働きに出ていくことに。……ともに同じ屋根のもとで暮らす家族の人数が多かった昔は、家族の中で役割分担ができていたのです。

旧鳥越地区、神子清水の集落の風景
それがさらに時代がくだり、農業の方を担っていた世代の方が亡くなり、山岸さんのお子さん・お孫さん世代となると一緒に2世帯・3世帯で暮らすことも少なくなります。
山岸さん:
「自分らの子供も(今は)家におらんがな。みんなどっか出て行ってそこで巣作りして、生活するわけやから、なかなか我々の跡を継ぐってことはまずないわな。だからここら辺、うちの町会はもうほとんどそんな家ばっかり。今もう集落に残ってるのは、60代、70代のおとっつぁん、おかっつぁん。じいちゃん、ばあちゃんは少ないし、それ以上の80代、90代はもう数人やな」
漢方に使われる薬草栽培をスタート。それでも現実は厳しく
山岸さんは現在(※取材当時)71歳。町会には40代以下はもう3人ほど。どんどん増えていく放棄されるしかなくなった土地を目の前にして、自分たちは何ができるのかーーそうして立ち上がった「今自分たちのところにある課題をどうにか解決しようよ、なんかやろうよ、という活動」が、神子清水薬草組合でした。
根の部分が生薬となる当帰(トウキ)という薬草を中心に栽培し、石鹸や入浴剤など製品化も自分たちで試みてきました。が、いくら価値があるものでも、なかなか利益を生むのは難しいという厳しい現実が・・・。皆ボランティアで関わってくれているという組合の活動。それでも、儲けはほとんど出ないと言います。
山岸さん:
「儲けが出るような商品ではない。当帰も手間がかかる。要は、耕作放棄地をなくするだけの活動やな(笑) そういうイメージや。……それでも、そういう活動を通じて、放棄地が普通の畑になればええなと」

現在の流通の限界として、商品として販売されるまでの過程で利益が上乗せされていく仕組み上、どうしても原材料をつくる一次産業が単価を上げづらくなる構造があります。
山岸さん:
「一番儲からんのは、原点の“ここ”や」
そう言って、山岸さんはテーブルをトンと叩き、少しだけ語気を強めました。
気候変動で変わる自然環境に対する対策、既存の作物をより効率よく、あるいはより品質よく生産する方法の模索と実践。近年いわれる「農林漁業の6次産業化」(※2)は、生産から流通まで一貫して実践し、地域資源から新たな付加価値を生み出すべし、と国が推奨する考え方ですが、実際には小さな規模の生産者が単体で行うことは非常に厳しいと言わざるを得ません。複数の事業者で手を組むことで進めていかないことには、単価の壁を突破するには不十分です。自分たちで商品化まで試みた結果をもつ山岸さんたち。その言葉は、重く響きます。
※2 「6次産業化」・・・「一次産業としての農林漁業と、二次産業としての製造業、三次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組」(「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化・地産地消法)より)

道の駅 一向一揆の里では、当帰の葉を使ったソフトクリームが食べられる(季節限定)
国をつくっているのは、民であり、“百姓”だ。
神子清水薬草組合の名刺に、「百姓ノ持地チタル国」という気になる表現が書かれていました。意図を尋ねてみると、山岸さんからはこんな答えが。
山岸さん:
「要は百姓が、国を作っとったわけや」

時は遡り1488年、守護大名であった富樫政親を破り、百姓=民衆の力で主権を得たセンセーショナルな戦い。それが、教科書にも掲載されている「加賀一向一揆」です。織田信長に制圧されるまで100年弱もの間、百姓が自治を獲得していたことから、加賀は後年「百姓の持ちたる国」と呼ばれるようになります。その最後の砦となったのが、鳥越城でした。
山岸さん:
「国を司っとるのは、政治家でもなんでもねえ、みんな民やがいね。民がその国を作っとるわけなんよな。その間におるのが行政。行政であり、議員がおって、今こう(政治を)やっとるわけ。
(かつての)国言うたら、みんな民、百姓が、年貢を収めて、年貢からいろんな事業をして、その国を作っていっとるわけや。それと変わらん、同じような意味合い」

国をつくっているのは、民であり百姓である。民主主義による政治が行われる現代では、なんということもないように聞こえる話ですが、当時からすれば圧倒的な権力・財力・武力の差がある統治を覆すなど、奇跡のような話。鳥越は、強い意志のもとで自由を獲得した“百姓”の魂が息づく土地だったのです。
「いくらでも作れる土台はある」
さて、話を現代に戻して、今の白山市・神子清水。異なる立場の者で手を組み、百姓精神で状況を打開する。ーーホーリーバジルは、そんな一つの事例といえます。
2025年で5年目となるホーリーバジルの生産。田んぼを一部ホーリーバジル用に転用したという敷地面積は、およそ200平米。肥料は鶏糞(※鶏のフンから作った有機肥料)を用い、化学肥料は一切不使用。1年目から360〜370キロほどの収穫量をあげたといい、2024年の出荷は600キロ。前年は300キロギリギリくらい・・・ということはつまり、まさかの倍の収穫量に!
畑は、ずっと作物を作り続けると、どうしても「地力」が落ちます。2024年は、3年間で収穫量の下がってきた土地に対して肥料で地力を補充するのに加えて、トラクターを導入。それまで手作業で行っていた時に比べて、面積はそのまま、畝の数を増やすなど、着実に収穫量を増やすための努力を続けています。
山岸さん:
「植えるタイミングを調整したら1年で2回収穫することも可能。いくらでも作れる土台はある」
・・・とはいえ、それだけ作っても販売先がなければ価値に転換されません。EarthRingとしては、精油としての香りの品質を保持するためには、鮮度が何より大事。ホーリーバジルを刈り取ったら、すぐにその日のうちに蒸留しないといけないのですが、他に取り扱う各種の草木も大本がひとりで蒸留している以上、スケジュールも待ったなし。量が増えても捌ききれない、というジレンマも。5年目を迎え、安定供給が叶うようになったからこその次の壁、といえます。


素材を無駄なく一番良い状態で蒸留し切れる量にも限界がある
「いい香りや」畑一帯がホーリーバジルの香りで包まれて
取材に訪れた9月初旬、収穫時期も終盤に差し掛かっていたホーリーバジルの畑は、控えめな紫色にうっすら染まっていました。
白い部分が花で、濃い紫色は萼(がく)
濃い紫色をしている部分は、遠目には花のように見えますが、実は萼(がく)。花は少し下を向くように控えめに小さく細かく咲きます。開花の最盛期はあたり一面が真っ白になるといい、たくさんのミツバチが集まるそう。夏場の刈り取りは、飛び交うミツバチの「ブーン」という羽音に囲まれて行われるといいます。

人もハチも、白山の大地が育てたこの植物からの恩恵をいただくのに懸命なのです
工夫の成果もあり、株も丈夫に、背丈も去年より高くなったというホーリーバジル。今年は腰の高さまで伸び伸びと育っていました。
山岸さんに案内いただいていると、隣の畑で作業をする方から「こんにちは〜」と声がかかりました。
「ここいい匂いするやろ」

山岸さん曰く、「その周辺で畑しとる人らは、『いい香りや、いい香りや』って言う」とのこと。秋の訪れを感じさせながらも、まだまだ眩しい日差しにわんわんセミが鳴く中、ホーリーバジルは爽やかに香って、周囲を幸せで包んでいるようでした。

打開策となるか!?ホーリーバジル活用の拡がりに期待を込めて
「不老不死の霊薬」としてインドで重宝されてきたホーリーバジル。神子清水という聖なる名を冠するこの地で、海を超えた彼の地の"holy"(聖なる)植物は、果たして地域・農業への救いの一手となるのか? その未来は、神のみぞ知る……否、私たち人間、一人ひとりが握っているはずです。

「神子清水」の名は、その昔大日川沿いに清水が湧き巫女が住んでいたという云われに因む
【この記事の関連商品】
取材・撮影執筆:吉澤志保

地方好き・移動好きの編集ライター。地域の活性化に関わる仕事に興味があり、取材を重ねるうちに人や地域の繋がりこそが大切だと考えるように。ただ書いたり撮ったりするだけでなく、誰かの思いや活動を伝える仕事を通して、対象となる人や場所との関係性を築きたいし、新しい価値を生み出したいと思っている。